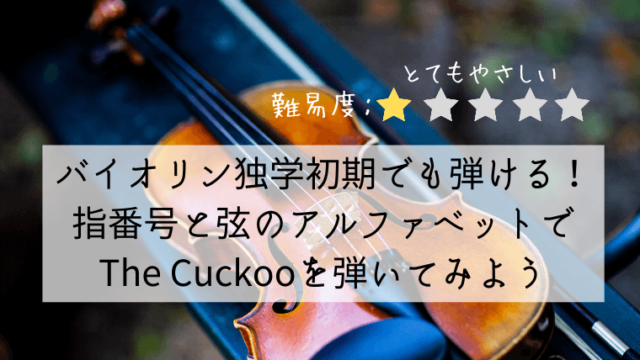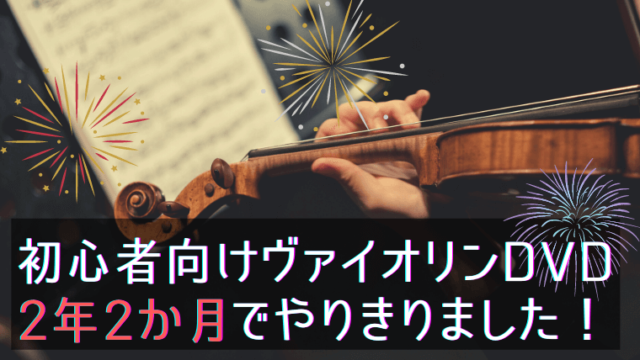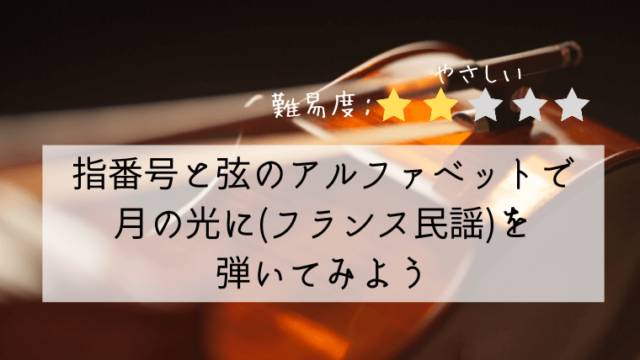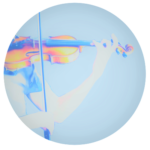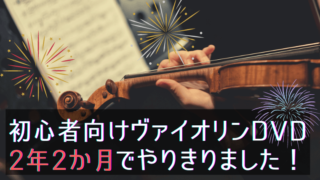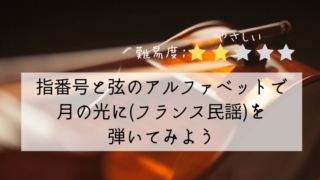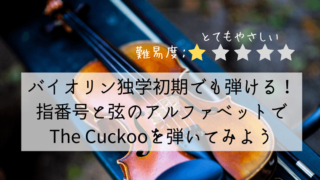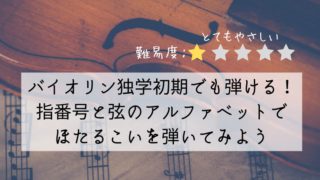こんにちは、Tsugumiです。
前回の記事ではエレキバイオリンの独学を始める際にどのくらい費用がかかったかというお話をしてました。

今回の記事では実際に自宅練習を開始してつまづいてしまった点について書きたいと思います。
バイオリン未経験者の独学はつまづくことが多すぎる
この一言につきます。つまづくポイント多すぎる。
「バイオリンの独学は難しい」という話を独学始める前から何度も目の当たりにしてきましたが、実際に独学をしてみて言えるのは「バイオリンの独学、本当に難しい。だってすぐ心折れそうになる」ということです。
バイオリンを一度も弾いたことのない私がエレキバイオリンで独学を開始して実際につまづいたところを列挙するとこのようになりました。
- バイオリンのパーツの名前がわからない
- 駒の立て方がわからない
- 弓の張り方・張り具合がわからない
- 調弦のやり方がわからない
- バイオリンの構え方がわからない
- バイオリンの音が鳴らない理由がわからない
- バイオリンから不快な音がする理由がわからない
バイオリン経験者の方からすると「え?そんなにつまづくの?w」という感じかもしれません。当方は楽器経験ほぼなしのアラサー。そいつが初見でバイオリン弾こうとしてこうなりましたすみません。
バイオリンのパーツの名前がわからない

まずバイオリンの最初のセッティングをしようと思って色々と調べるんですけども、そこに書いてある単語の意味がわからないところからつまづきました(早すぎる)
弓や弦、指板とかはわかるんですけど、弦楽器を扱ったことがないからか「ペグ」すら何のことなのかわかりませんでした(ペグ?犬の種類?みたいな)
駒も何のことなのかわかりませんでしたね…くるくる回るコマを思い浮かべて、ペグのことなのかなと思ったりもしました(今はもう大丈夫ですw)
単語の意味がわからないとやり方を調べて読んでみてもどうすればいいのか全然わからないので、最初は何かを調べる度にわからない単語が出たら意味を調べて理解しての繰り返しでした。
駒の立て方がわからない
最初に購入したエレキバイオリンは既にゆるく弦が巻いてあり、駒は自分で立てるようになっていました。
よしでは駒を立てて弾いてみよう!と思うもまず駒の向きからしてわからないところでつまづきました。
特に説明書もなく聞ける人も居ないので、ネットで調べるしかなかったのですが、
駒の高さが高いほうがG線になるようにすればいいのか。G線ってどこ?
→ G線は一番太い弦なのか。一番太い弦どこ?
→ 一番左の線が一番太く見える気がする。じゃあ駒の高いほうが左に来るように立てればいい…んだよね?(自信薄)
パソコン→バイオリン→パソコン→バイオリンと往復しながらようやく駒を立て、しかし本当にこの向きで合っているのかわからないという圧倒的な不安がありました。
念の為、改めて今確認してみたら合っていたのでセーフですが、当初はそれすらも確信が持てませんでした。
弓の張り方・張り具合がわからない
弓についてもつまづきました。
どうやったら弓の毛が張れるのか、そしてどのくらい張ればいいのかがわからないんですよね。
調べると張り方はすぐわかったものの、張り具合については「フォルテで弾いた時に弓中が弦にこすれない程度に張る」という情報見て「何かの呪文なのかな?」と思いました。
バイオリン教室であれば恐らく初回に先生から「このくらいの張り具合で…」と教えてもらえるのでしょうが、独学だとこんなところですらつまづいてしまうんですよね。
調弦のやり方がわからない
調弦もバイオリン未経験者且つ他の弦楽器を扱ったことのない自分にはなかなか大変でした。
まずG線、D線、A線、E線のそれぞれの音がわからないところから始まりました。
調べたところG線がソ、D線がレ、A線がラ、E線がミということは分かったものの、どんな音だったっけ…そうか手元にピアノもない!どうしよう!となっていました。
ありがたくもスマートフォンのバイオリン用チューニングアプリでそれぞれ音が出せることがわかったので、音を聞きつつ弦を弾きつつペグを締めていったのですがここがもうダメダメでした。
- ペグが固くて回らない
- ペグを回す方向がわからず、締めるはずが緩めてしまう
- 逆に音を低くしたいからペグを緩めようと思っているのに締めてしまう
- どのペグが何線につながっているのかわからず、調整したい弦と別のペグを一生懸命締める
- アジャスターで微調整しようとするも回す方向がわからず(以下略)
- 全部チューニングし終わった…と思って最初の弦を弾くと既にペグが緩んでおりやり直し
- 弦を弾いて出している音が、目的の音より高いのか低いのかわからない
思い出しながら書き出してみると、ここもかなり心折れそうでした。
ペグをどのくらいの力で押し込めばしっかり締まるのかも手探りで、しっかり締めたはずが緩んでしまい最初からチューニングをやり直すということを繰り返していて、いつになったら弾けるんだろう…という気持ちでした。
バイオリンの構え方がわからない

チューニングができて、いざ弾いてみよう!と思った時もつまづきました。バイオリンの構え方がわからないんですよね。
首と左手でバイオリンを支えて、右手で弓を持つのだけはわかるけれども
- そもそも肩当てってバイオリンにどう向きにつけるの?
- バイオリンを首で挟むってどういう角度で?
- 左手ってどこを持つの?指はどう握るの?
- 弓ってどう持つの?
調べたとおりにやってみて鏡を見てみても、正しいかどうか自分では判断できないんですよね。未経験だと特にわからない…これもバイオリン教室に行っていれば初回のレッスンで先生が教えてくれるんだろうなと思いながらやっていました。
バイオリンの音が鳴らない理由がわからない
最も心折れそうだったのがこれです。
バイオリンを弾いてみても音が鳴らない。しかしその理由がわからない…
ちゃんとバイオリンの音がどうやって鳴るのか仕組みを理解してから始めろよ!という感じなのですが、当初は弦を弓でスッとすれば何事もなく音が鳴ると思っていたんです(アホ)
松脂がちゃんと塗れていない→音が出ず心折れそうになる
ここは本当に泣くかと思いました。
(記憶が薄れてきてますが若干泣いてたかもしれない)
調べた通りの手順で弓に松脂を塗っているのに「スーッ」っと弦と弓が擦れる音がするだけで全然音が鳴らない。
改めて調べると「買ったばかりの弓は松脂が付きづらいからしっかり塗ろうね」という情報があり、なんだー塗り方が足りなかっただけかー!と思って再度松脂をよく塗って弾いてみてもやっぱり音が出ない。
「えっ…こんなに一生懸命塗っているのに…?」と思いながら、そこから松脂を塗る→弾く→音が出ない→松脂を塗る→弾く→音が出ないの繰り返しでした。
極力凹まないように努めて明るく就寝した翌日、どうも松脂の表面をヤスリで削ると付きやすくなるらしいと知り、ヤスリをかけてから塗ってみたら、今までと明らかに手応えが違いました。
もしかしたらこれで音が鳴るのかも!と思い弾いてみたら、ようやく音が鳴って感動。仕事から帰って2日間奮闘していたので、音が出ただけなのにすごく感動していました。
弓の毛に松脂の粉がつくことで弦にひっかかるようになって音が鳴るんだということをちゃんと理解していれば、松脂が弓の毛にぜんっぜんついていないこともパッと見てわかっただろうに…と今となっては呆れてしまいますが、当時は「なんで音がならないの?松脂塗ってるのに音が出ないのは不良品だからなの?」なんて、ありえないことを考えてました。
バイオリンから不快な音がする理由がわからない
ここまでに挙げたつまづいたポイント達は独学でもなんとかクリアしてこられたのですが、不快な音がしてしまう点についてはバイオリン教室に行かなければ理由がわからないままだっただろうと思います。
バイオリンを弾いてて音が抜けてしまったりキーキーいったりして不快だなと思いつつ、時折上手く弾ける時と、そうでない時に何が違うのか自分では全くわからずでした。
調べてみると「ちゃんと弦を捉えられてない」というような情報があるものの「弦を捉えるってどういう状態…?」という感じで、文章を読んだだけでは全然理解できない。
私の場合はその後、バイオリン教室に通うことができたので教室の先生がすぐに治してくれましたが、もしあのまま自分1人でずっとやってたら今頃はバイオリン続けてなかったかもなと思います。
まとめ:バイオリン教室で当たり前に教えてもらえることでも独学の場合はつらいことが多すぎる
以上、未経験でバイオリンの独学を始めてつまづいた点を列挙してみました。
こうしてみてみると、最初からバイオリン教室に行っていれば当たり前に教えてもらえることばかりなのですが、独学だと自分で調べつつやりつつになるので一度深みにハマってしまうと抜け出せなくなってしまいがちです。
私も最初は独学からはじめましたが、今となっては独学をするにしてもまずはバイオリン教室に行って自分でバイオリンの面倒が見られるようになるまでは先生に教えてもらう方が絶対に良いだろうなぁと思います。
バイオリン演奏は本当に楽しいです。
初期の段階でつまづいて練習を辞めてしまうと、ものすごく勿体ないくらに楽しい。
もし独学にするかバイオリン教室にするか悩んでいる場合は、未経験者であればまずバイオリン教室に行ってみることを強くおすすめしたいです。